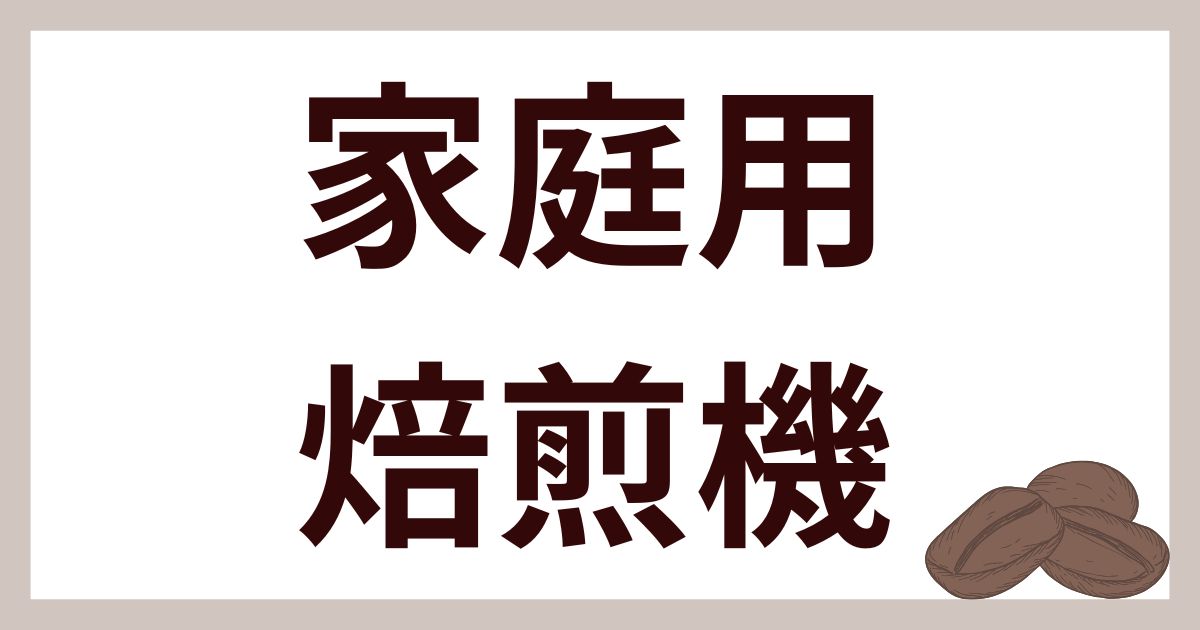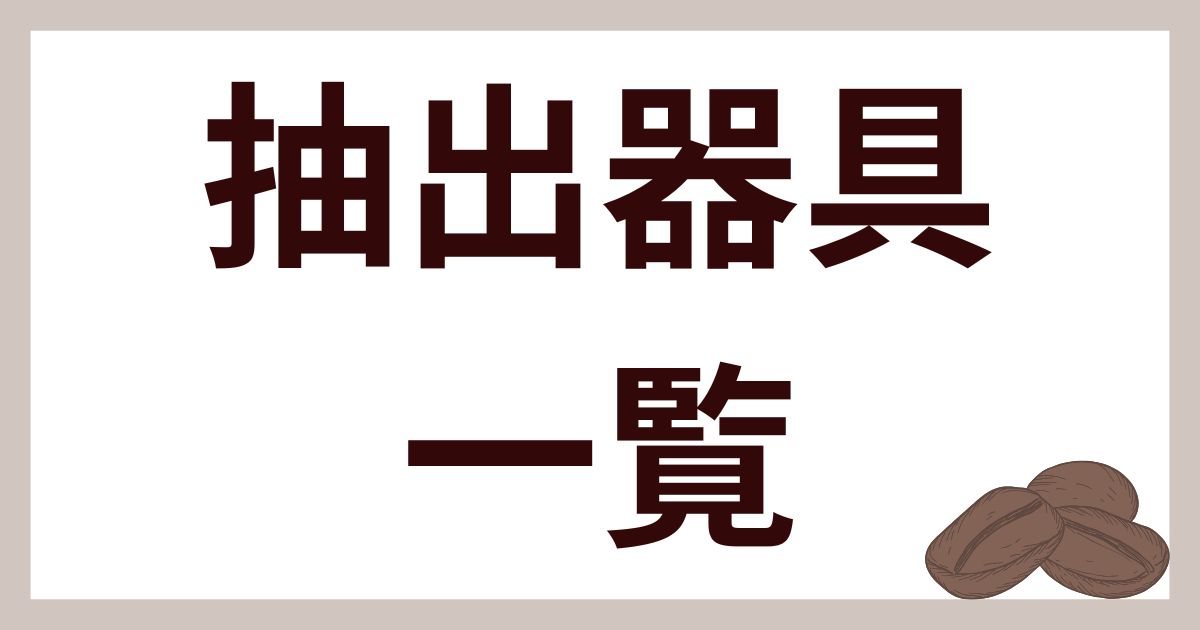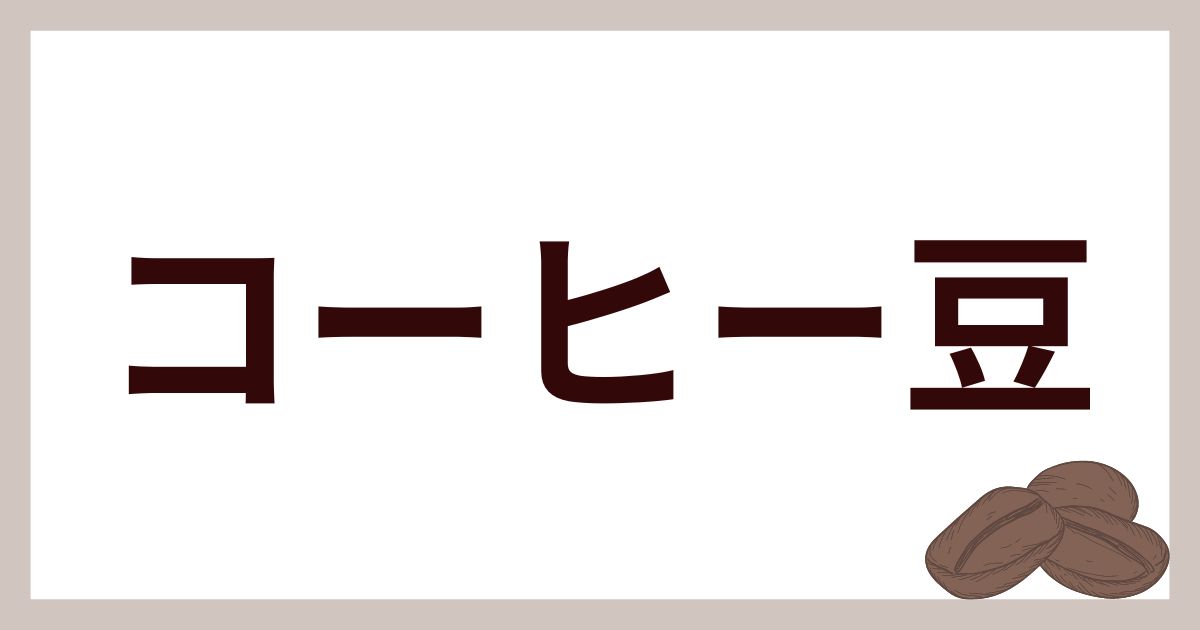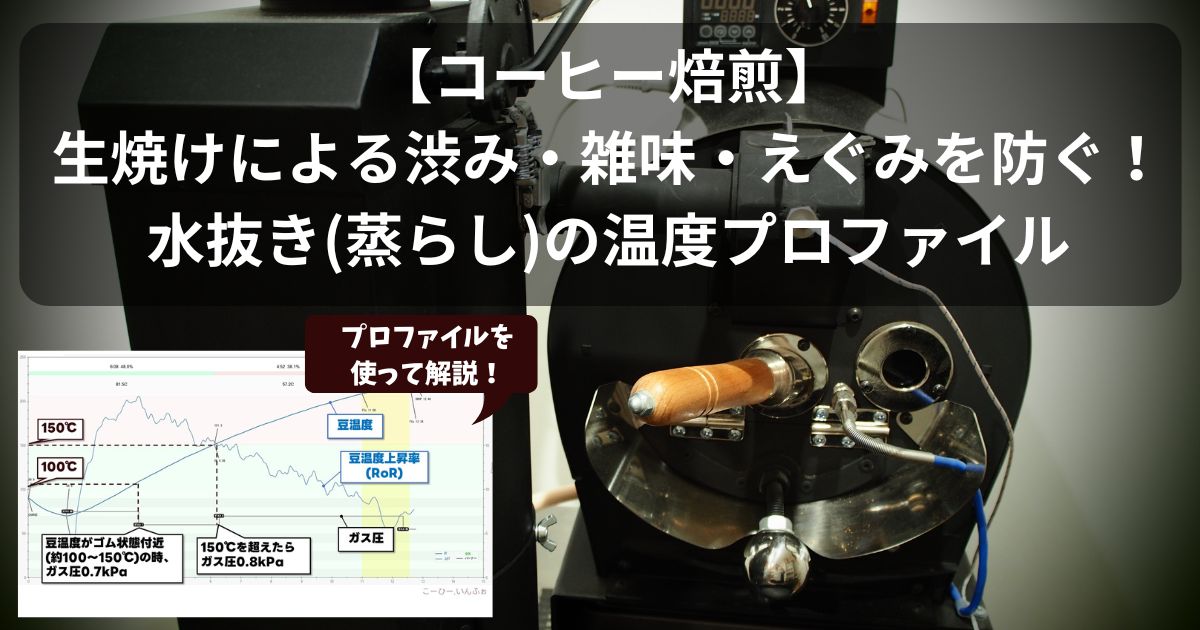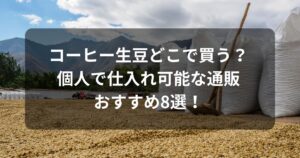おうちコーヒー焙煎歴10年目のでぃーんです。
コーヒー焙煎初心者の頃は、

自分で焙煎したコーヒーが、嫌な渋み・雑味・えぐみを感じて、まずくて飲めない…
という失敗をすることがあるかと思います。
これは、いわゆる「生焼け」という状態で、焙煎初期の温度プロファイルに問題があり、
コーヒー生豆に含まれている水分が抜けていないことが原因です。
私も焙煎を始めて半年くらいは、生焼けの症状に悩まされることがありました。
本記事では、科学的にわかっている生豆の変化を根拠に、
どのような温度プロファイルにすると水分を抜きやすいか考察し、
実際に私が採用している具体的な温度プロファイルを紹介します。
私は焙煎量MAX 500gのワイルドコーヒー製 アポロ焙煎機(現マーベラス焙煎機)を使用しているので、
以下のような焙煎量1kg以下の小型焙煎機を使用している方の参考になるかと思います。
- ワイルドコーヒー ナナハン焙煎機
- 富士珈機 ディスカバリー
- 富士珈機 R-101
- Aillio Technology Bulletシリーズ
- 煎りたてハマ珈琲 HCR-1000
- KALDI Fortis
また、温度プロファイルが良くても、生豆の品質が悪いとおいしいコーヒーにはなりません。
私が実践している、生豆の仕入れ方、保存方法についてもご紹介します。
焙煎による生豆の変化
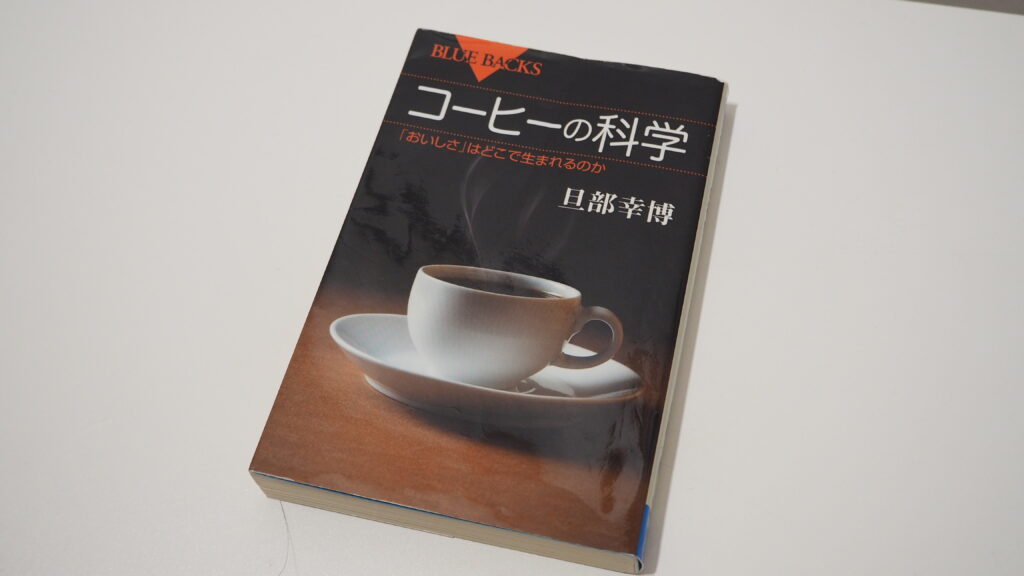
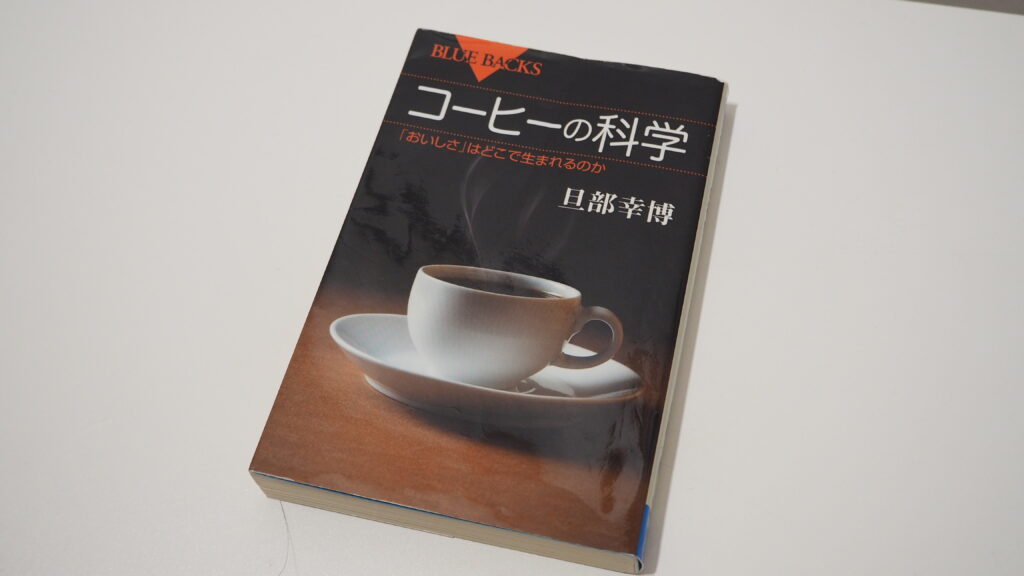
書籍「コーヒーの科学」を参考に、焙煎による生豆の状態変化を、
- 温度
- 生豆に含まれる水分
に着目してまとめると、以下の表のようになります。
| 加熱時間 | 豆温度 | 含水量 | 状態 |
|---|---|---|---|
| ~5分 | ~70℃ | 10%~ | ガラス |
| 5~11分 | 70~140℃ | 4~10% | ゴム |
| 11分~ | 140℃~ | ~4% | ガラス |
この表は、焙煎の時間経過とともに豆温度が上がって、生豆の含水量が減っていくと、生豆に物理的な変化が起こることを示しています。
コーヒー生豆は常温では「ガラス状態」と呼ばれる、とても硬い状態です。
加熱して豆温度が約70℃、含水量が約10%を境に、柔らかい「ゴム状態」に変化します。
この変化を「ガラス転移現象」と呼び、コーヒー生豆を焙煎する際の物理的変化として知られています。
さらに加熱を続けると、豆温度が約140℃、含水量が約4%を境に、再び「ガラス状態」に変化します。
生豆の水分が抜けやすいのは、「ゴム状態」の間です。
したがって、生豆の水分を効率よく抜くには、
ゴム状態の時間を長めにとる
ことが良いと考えることができます。
長時間焙煎するほど良いのか?
コーヒー生豆から水分を抜くために、火力を弱くし、長時間焙煎すれば良いのでしょうか?
答えはNoです。
理由は、焙煎時間を長くしすぎるのは、以下のデメリットが考えられるためです。
- 香り成分が飛びすぎてしまう
- 水抜きの時に高温多湿の領域に長くとどまると、渋み、酸味の強い成分が増加する
- 良い香味成分を作る加水分解が生じなくなる
コーヒーの香り成分は、焙煎時間が長いほど発生しづらくなります。
また、焙煎初期の水抜きの時に高温多湿の領域に長くとどまりすぎると、
クロロゲン酸の加水分解が促進され、強い渋みのカフェー酸とシャープな酸味のキナ酸が増加してしまいます。
さらに加水分解には良い効果もあって、たんぱく質や配糖体の加水分解で香味が強まります。
結局、焙煎時間は長すぎても短すぎてもダメで、
作りたい味に合わせて「いい具合」に火力、焙煎時間を決めていくしかなさそうです。
ただし、渋み・雑味・えぐみに悩まされている場合は、ゴム状態の時間を長くするのが基本方針になります。
水抜きの具体的な温度プロファイル


2016年から焙煎を続けてたどりついた、私が使用している水抜きの温度プロファイルを紹介します。
水抜きは、「蒸らし」「Drying phase」などとも呼ばれますが、本記事では同じ意味として扱います。
使用した焙煎機などの条件
- 焙煎機:アポロ焙煎機(現マーベラス焙煎機)
- 方式:半熱風式
- 熱源:都市ガス
- 生豆:エチオピア ゲイシャ G3ナチュラル
- 生豆投入量:250g


約20分かけて200℃まで焙煎機を予熱します。
その後火を止めて、90℃まで温度が下がったら生豆を投入します。
生豆投入量が250g以下の場合は、火はつけずに豆温度が70℃まで下がるのを待ちます。


豆温度が70℃になったら、着火します。中点はほぼ70℃になります。
このとき、ガス圧は約0.85kPaです。
少し強めの火力で、生豆をゴム状態にするイメージです。
火力の目安は、豆温度上昇率(RoR)の最大値が約20℃/min.になるようにします。
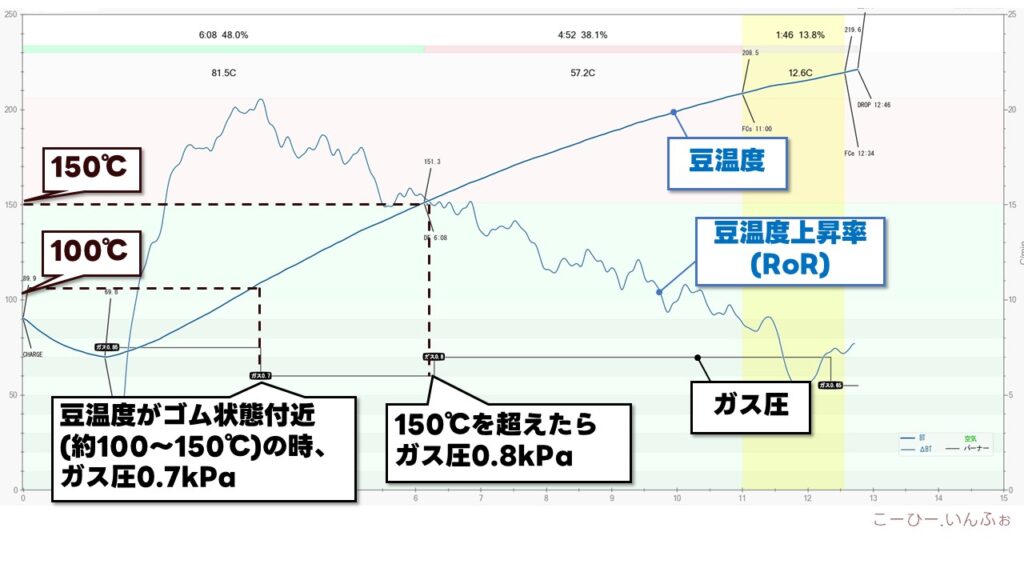
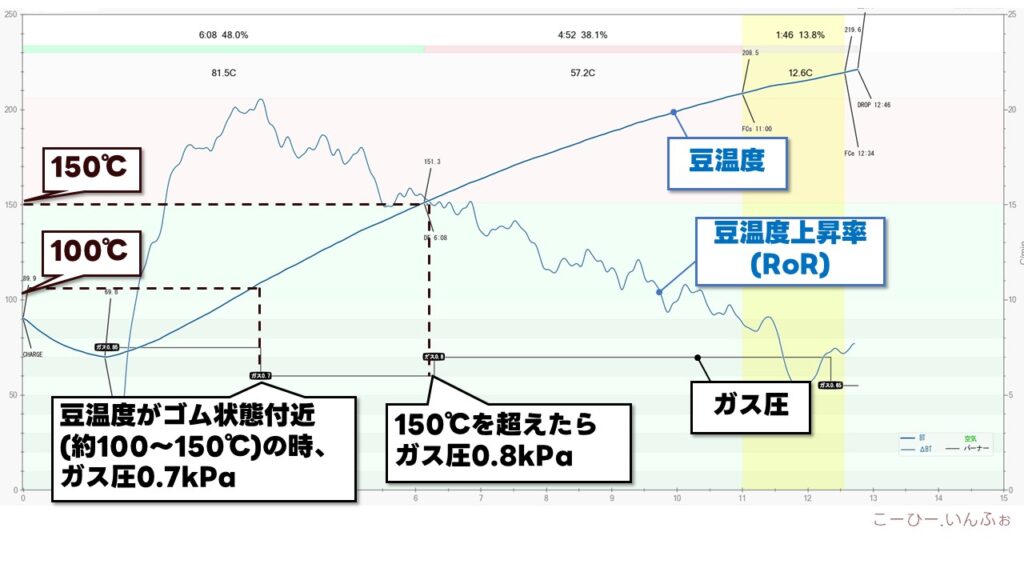
本記事のポイント、水抜きです。
豆温度が約100℃になったらガス圧を0.85kPaから0.7kPaに絞ります。
生豆がゴム状態になっている時間を長くとるため、少し火力を弱めるためです。
焙煎時間6~7分の間に、豆温度が150℃に到達する火力のイメージです。
この時、RoRは徐々に低下していきます。
また、150℃を超えたらガス圧を0.8kPaに戻します。
上記は一例ですが、どの生豆でもおおむねこのプロファイル設計で生焼けは発生せず、おいしく焼けています。
品質の良いコーヒー生豆の仕入れ方


焙煎の温度プロファイルがうまくいっても、
そもそも生豆の品質が悪いと美味しいコーヒーにはなりません。
そのため、品質の良い生豆を扱う業者から仕入れることが重要です。
個人で焙煎を楽しんでいる方は、通販で生豆を買うことがほとんどだと思いますが、
仕入れ先による品質のバラツキは大きいです。
私は焙煎を続ける中で、よい業者、よくない業者含め10社以上の業者から生豆を購入してきました。
その中から本当にオススメできる業者をまとめたので、



使っている生豆の品質に絶対の自信は無いかも…
という方は、ぜひ下記の記事を参考にしてみてください。
コーヒー生豆の劣化


仕入れるコーヒー生豆の品質と同様に大切なのが、生豆の劣化についてです。
コーヒー生豆は適切に保存しないと、半年くらいで味が劣化する場合があります。
ここでは結論だけ書くと、
真空パックで保存
することが、自宅でコスパ良く対応できる生豆の保存方法と考えています。
詳細は下記の記事にまとめたので、生豆の保存に関して気にしていなかった方はご一読ください。
まとめ
生焼けによる渋み・雑味・えぐみの原因を防ぐための、水抜きの温度プロファイルを紹介しました。
焙煎そのものの他に、生豆の品質が悪いことが原因の場合もあるので、
品質の良い生豆の購入先は下記の記事を参考にしてください。
また、劣化を防ぐための生豆の保存方法に関しては、下記の記事を参考にしてください。
その他のコーヒー焙煎の失敗例として、よく挙げられる
味が抜ける・薄くなる・フラット・スカスカ
という症状については、以下の記事で原因を考察しました。
また、焙煎量が違う場合の調整方法は、下記の記事でまとめました。
焙煎プロファイルを考える参考にしていただければと思います。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!